この検査を受診したきっかけを書くと長くなるので、先日、子供のSーM社会生活能力検査を実施してきたことを報告します。色々とエピソードが重なってきまして、療育手帳の申請を行った際に、こちらの検査を受けに行きました。
結果の捉え方が難しいのですが、結論として療育手帳は交付されませんでした。
療育手帳申請の結果
検査時間が大幅にかかったので、結果は電話対応にすると一度決まったのですが、
もう1人の職員さんより10分だけお待ちいただけませんか?と言われ、結局、対面で結果を伺いました。職員さんが対面を希望されたのは、息子が非常にグレーゾーンであったからのようです。本当にギリギリだと言われ、療育手帳が交付されないことをどう感じるか、尋ねられました。
元々、色々深く考えない私なので、その場で思いついたのは下記の懸念点でした。
療育手帳が認められなかったことの懸念点!?
懸念点:今後の進学をする上で、合理的な配慮が必要な時に、”療育手帳”がなければ、単なる親の心配過ぎや、場合によってはモンスターペアレンツ扱いを受けるのではないか。担任の先生も多忙な中で対応が必要な子の優先順位が生じる。対応が必要な子の中に入れないのであれば、気がかりである。
気になる点:他の地域ではIQだけで切り取らないと聞いている。IQがとても高い子供も療育手帳が交付されている事例を聞いていて、〇〇市がIQベースに判断していることには疑問が残る。転出入も多い地域なので、転入の方と〇〇市で新規申請した方とで待遇に齟齬があるように感じる。
調査結果は来月コピーをいただきにいくことになったので、息子の伸ばすべきスキルを確認し、療育活動にトライしていこうと思います。
結果を見ないと正確にはわかりませんが、視覚から得る情報は年齢並みであること、一方聴覚から得る情報や、説明の仕方に関しては、3年程乖離があるとのことでした。
これは実は、テスト結果前に職員さんと面談中、私自身が感じていることで話していた内容と合致するので、私が感じていたことと検査結果が合っていたという1つの基準が出来たのはよかったです。
職員さんには過度に褒めていただきました。(療育手帳交付出来ないから気を遣ったのかしら。)
ここで、少し楽観的な私は、私なんて、健康診断の結果で”ー〇〇歳”と出る(忖度健康診断か!?)と疑いつつ、内心喜んでいたんだけどな、学生時代の数年の差はそうもいかんよな〜どこかで実年齢と追いつくことはないんかな〜と素人的には思いました。
しかしやはり、楽観視できないのは、受験というハードルがあるからだとは思います。親として横並びで比べるつもりはなくても、受験という横並びの仕組みがあるという事実。つい、本人のできないことを数えてしまいがちですが、大人の私にも苦手なことは数多くあります。本人が好きなこと・スキルを伸ばしながら、学力ではなく”生きる力”をつけられるようにサポートしたいと思います。
支えてもらえる支援が多くても少なくても、どんな状況であっても、子供が自立する年齢になるまでに1つ1つ出来ることが増えるように親として支援をすること、周りのお友達や同級生と横並びで比べることはせず、本人の1年前・半年前・1ヶ月前との変化・成長にフォーカスし、良いところを見つけてしっかり良いポイントを伝えることは変わらず意識していこうと思います。

私が最終的に相談したのは、小児科医
私は、予防接種等でかかりつけ医となっていた小児科が”育児相談”という専門外来を用意されていて、予約したことがきっかけとなり、療育に関わる活動がスタートしました。今回、我が子には療育手帳は交付されませんでしたが、医師の診断をきっかけに、放課後デイサービスを受けられるようになり、現在はSST(ソーシャルスキルトレーニング)を受けています。我が子は高学年になってから療育活動をスタートしましたが、もう少し小さな頃から気づけなかったかな?と感じることはあります。
実は、低学年の頃、市の療育相談機関を訪問したことがあります。すでにいくつかエピソードがあったからなのですが、その機関の職員さんからは、”お母さんが診断等受けたいのであれば、診断は付くと思いますが、そこに意味はありませんよ”と言われました。なんでしょう。
その時の私は、別に診断が付くとも、診断を付けたいとも思っていなかったわけなのですが、なんだか、親として何かのせいにしようと思われるんだと悲しい気持ちになってしまいました。それと同時に、色んなお子さんに対応している機関の方がそういうのであれば、そのまま日々の様子を見て支えていこうと思ってしまいました。(その後、googleのクチコミには同じような対応をされた親御さんの投稿があり、その職員さん特有の対応であったようです。)
今、振り返るとあの低学年の頃から活動していても良かったのでは?とは思いますが、療育を進めず様子を見ると決めたのは自分です。療育に対する自らの心のハードルがあったのかもしれません。
経験から学んだことは、”あれ?”と思ったら、複数の方のアドバイスを聞くことです。あと、その方が所属している組織の特性を踏まえることです。民間なのか、公的な機関なのかという視点、専門的資格を有しているのか、有していないのか、多方面からのアドバイスを受けると道が開いていくと感じています。私は、まだまだ療育の世界を学べてないので、今後学びを増やしていきます。
※療育手帳の検査について
今回、地方自治体が実施する療育手帳の検査を受診しました。子供と別室で対応していたので、結局子供が具体的にどんな検査を受けたのか分かりません。ネットで調べても具体的なものはあまり見つけられませんでした。そのことをお世話になっている発達心理センターの先生に伺うと、理由は、オープンにすると、療育判定を受けたくない親御さんが子供にその内容を特訓したり、療育手帳を取得したい親御さんはその逆の対策をするからだそうです。
そ、そっか。そんな意図ではなく、単純に自分の子供のどの部分を伸ばす必要があるか知りたかっただけなのに。と理由に納得しました。
この記事を書いた人
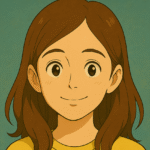
-
こんにちは!
40代3児のワーママ Ranisaです
日々の暮らしを綴らせてください
笑顔で楽しい日々を送りたいと思っています。
最新の投稿
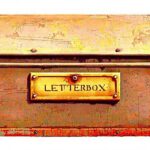 子育て2026年1月31日我が家のお手紙ボックスの工夫
子育て2026年1月31日我が家のお手紙ボックスの工夫 仕事2026年1月29日外勤 営業職の必需品 Anker製品
仕事2026年1月29日外勤 営業職の必需品 Anker製品 子育て2026年1月27日忘れ物が多い小学生の息子 対策5選
子育て2026年1月27日忘れ物が多い小学生の息子 対策5選 仕事2026年1月25日社内の面談で言うべきことは何なのか?
仕事2026年1月25日社内の面談で言うべきことは何なのか?



コメント